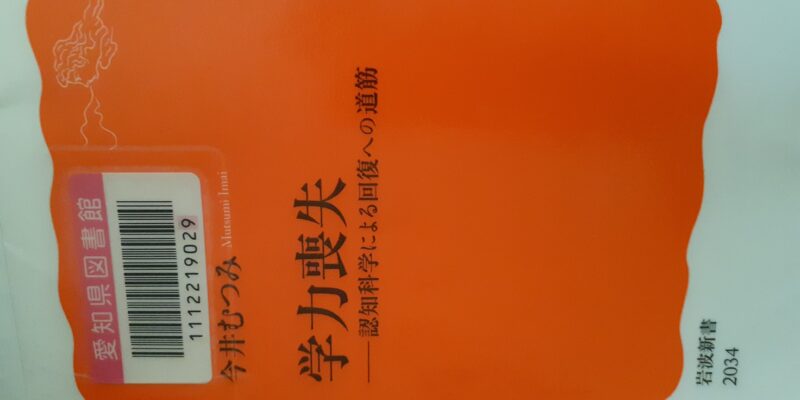
地図を読めるってどういうこと?
〇読図について
最近はすぐれた地図アプリができたおかげで、ふつうの山道を歩くだけなら、それほど地図(地形図)を読むということが必要と思われなくなってきたように思います。
それでも、「地図を読めるようになりたい」という人はいる一方、ひととおりの勉強をしても、結局現場では地図アプリしか見ない人が多いような気もしています。
よく考えると、「地図を読めるようになりたい」という人がどうしてそう思ったのか、どういう風になりたいと思ったのか実はよく聞いたことがなかったことに改めて気が付きました。また、勉強したはずの人が、その後もあまり山で地図を見ないのは、とりあえず地図アプリがあればなんとかなるからなのか、地図の有効性を実感できないのか、あるいは思ったよりわかりにくいからなのか、そのあたりも深く聞いてみたいところです。
〇地図の効用
地図の効用としては、「スマホの電源が落ちた時にどうするんだ」とか「厳冬期は凍傷になってしまうからスマホなんか触っていられないぞ」などとよく言われます。確かにそういったときに地図が読めないとたちまち困ってしまうのは誰でもわかります。
それ以外にも、地図は現在地を把握するためだけでなく、その先の地形を予測できるので、現場での行動指針を決めていくための大事な判断材料になりますし、山に行く前には、行程全体を俯瞰して、危険なところや迷いやすいところをあらかじめ予想し、山行計画を立てるうえで、地図はとても有用です。
ほかにも地図を眺めることで有用なことはいろいろあると思います。
〇「地図を読める」とは?
では、「地図を読める」とはどんなことをいうのでしょうか。ここは地図の達人に聞いてみたいところですが、「読める」(=わかる)とはどういったこと(状態)をいうのか、実は人の頭の中のことなので、わかったようでわからない。地図のしくみや約束ごとをひととおり理解していたつもりでいても、より深い読み方をする人と話していると、自分は未熟だったと思うことはよくありました。
最近『学力喪失』いう本を読みました。多くの小学生が、3,4年生になり、分数の操作など、算数の抽象的な概念ができきた途端、つまずいてしまう(「9歳の壁」というらしい)のはなぜか、ということを認知科学の観点から考察した本です。
そこでは、単に抽象的な概念や記号を操作する方法を知ることだけでなく、抽象的な概念や記号が身体や経験に紐づけられ、地についたものになっていく過程を経験することが「生きた知識」を生んでいくのだと書いてありました。
また、人間の認知のしかたは、基本的には非常に直感的な認知方法をとるけども、いったんそう思っても「いや待てよ…」と自分の直感を振りかえり理性的に検討する「メタ認知」という認知方法もあわせて持っており、直感⇒メタ認知での直感の修正といったように、ふたつの認知方法を行き来することを重ねていくことで、すぐれた直感が養われていくとも書いてありました。
この本は、主に数学的な抽象概念を「知る」「わかる」とはどういうことか、どうして多くの小学生がつまずいてしまうのか、ということがテーマの本ですが、「知る」や「わかる」の本質を突いている気がしました。
私の知るヤブ山の達人は、地図をみて、「ここは無理そうだけど、ここなら行けそうだ」などと言いましたが、そう思った理由を聞いても、困ったように「だって(地図を)みたらそう思えるから」としか説明してくれませんでした。その人の山登りは道のないヤブ山を目的地(多くは山頂)に、どこから入り、どういう経路で行けばたどり着けるか、山に行く前に地図とにらめっこすることで始めるそうです。
地図というのは、一定のルールで、本来立体のものを無理やり?平面に落とし込んだものです。いわば記号の世界です。思うに、言葉でうまく説明できないにしても、その人の場合は、地図という記号の世界が、きっと自分の身体の感覚や経験につながっていたのではないかと思っています。
知識として地図の見方を知ることはもちろん大切ですが、山に行く前に地図をじっとみて地形や斜度を想像し、行ってみて地図と現場を照らし合わせ、直感と実際がどう違ったのか振り返ってみる、などの作業を繰り返すことで、記号で書かれたものが自分の身体に紐づけられ、落とし込まれていく、これが「知っている」「わかった」という感覚なのかな…と想像するのですが、みなさんいかがでしょうか?
参考『学力喪失 ―認知科学による回復への道筋』 今井むつみ著 岩波新書
